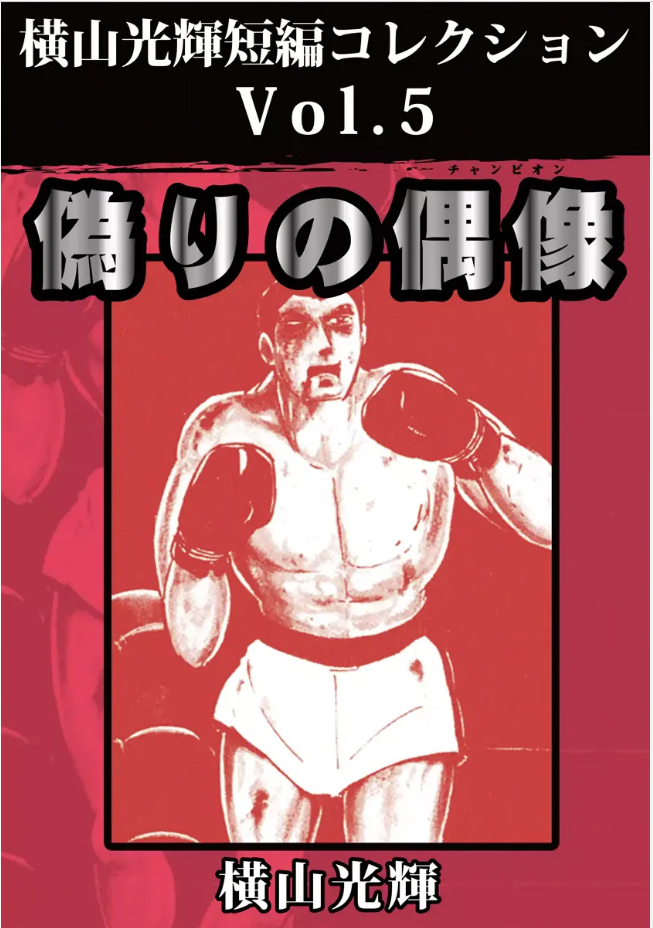横山光輝作品で珍しいセクシー美女表紙です。思いっきり峰不二子風ですなあ。
物語はふたつ。
表紙は1話目の「ぶっそうな奴ら」のものです。
ネタバレしますのでご注意を。
「ぶっそうな奴ら」(1969年週刊プレイボーイ)
そして中身もやはり峰不二子風&ルパン三世風作品であった。
警備会社の現金輸送車を襲う強盗団の話なのだ。
計画を立てたのが不二子風セクシー美女のマリでその相棒となった男が指示を出していく。
ふたりが見込んだ腕利きを集めて強盗団を作り計画を実行する。
これも60年代後半当時流行った一種の冒険ものなのだ。
主人公はとりあえず山崎五郎という男だろう。女を抱いては金をもらっているという「ケチな男」だが運転技術だけは一流中の一流(自己申告)でそれを見込まれて強盗団に加わる。他もルパン三世や多くの銀行強盗話に必要な腕利きメンバーが揃えられる。
とはいえそこは横山光輝なので軽みは少なくじっくりと進んでいくのが逆にちょっと面白い。
不二子的セクシー女性役のマリもやたらと薄着で体の曲線を見せびらかしてはいるものの相棒の男とどんな関係かすらも判らず何らかの場面もない。強盗の理由もその会社が父親の死を軽く見たための復讐という重いもので「おふざけでやっちゃおう」みたいなノリがない。しかも高みの見物じゃなく彼女がかなりの割合で働いているのだ。男たちが命懸けで奪ったものを横取りしていく、という女じゃないってのがちょっと悲しい。
この計画自体をどうこう言ってもしょうがないんだけどあの細い山道を進む計画を立てたのはどう考えても納得できないんだよなあ。まあまあかつてのこうした冒険アクションものというのはそうした穴だらけの設定なんだけど雰囲気だけを楽しむものだった、と思うしかない。ハラハラドキドキさせるのが目的なんだよな。
で、現金輸送車を強奪したものの雨になったせいで地盤が緩み細い山道を進むことができずボスの男は「五郎、車をおっことしな」というのだ。
車は崖下に落下し燃え上がる。
ボスは皆に「こんどもっとうまい話をみつけてくる」と別れを告げるのだった。
金は手に入らなかったけど誰かが死ぬわけじゃなくやっぱりハラハラドキドキが目的の冒険ものなんだろうな。
第2話
「偏愛」(1969年8月号ファニー)
「ファニー」ってなんぞやと思い検索しました。1969年に創刊した少女向け雑誌で1970年には編集長の急死(!)もあって休刊。もともと売れ行きが芳しくなく虫プロ商事の倒産の原因の一つともなったと書かれており「げえっ」となった次第。
休刊後に「月刊ファニー」となるのですが本作は「ファニー」だった時に掲載されているようです。つまり少女マンガ作品という位置づけでしょう。
「ファニー」&「月刊ファニー」には手塚治虫・石ノ森章太郎・永井豪・あすなひろし小島剛夕・ジョージ秋山・松本零士から牧美也子・みつはしちかこ・岡田史子・水野英子・山岸凉子・竹宮惠子・大島弓子・矢代まさこなどなどそうそうたるメンバーが執筆していてちょっと豪華すぎる気もする(それが原因か?)(青池保子の単行本未収録というのもあるよ)
そんなマンガ誌に掲載された本作であるがこれがまた横山作品としては稀有な存在なのではないのでしょうか。
ネタバレしますのでご注意を。

冒頭、電車からひとりの老女が降り立ち「ばあちゃんここだよ」と迎える男の子がいた。
老女は美しい女性に声をかける「まあおじょうさま」
「おじょうさま」と呼ばれた女性は老女を「かね」と呼ぶ。

この1ページのやりとりで老女と若い女性の関係性がすっかりわかってしまう。なんという上手さ。
が、その後の老女のモノローグで「おじょうさま」がかわいらしいけど残忍な性格だったと知らされる。
おじょうさまは小動物を無惨に殺しては喜ぶような少女だった。
八つになった時、おじょうさまをひどくいじめたわんぱく坊主がその翌日に池でおぼれ死んだのだ。
そして18歳になったおじょうさまは変な男と恋をしてお父様に怒られた。父親はその翌日事故死したのだった。
さらにその男がやはり悪い男だとわかりヒ素で亡くなってしまった後、かねは暇をもらったという。
そのおじょうさまが今は化学博士と結婚して暮らしていると聞いたかねは心配になりおじょうさまの家を訪問するのだった。
化学博士が劇薬を使用して実験をしていると聞きサスペンスは高まっていく。かねはおじょうさまを止めることができるのか。
そして不安に満ちたかねの表情が実は彼女自身の殺意からくるものだったと最後に読者は知らされる。
語りがかねからおじょうさまへと変わり実はこれまでの事件の説明は「かねが思っていたもの」であり実際はその裏返しになっていたのだと気づかされる。
こうしたサスペンスストーリーは女性好みだと横山氏は思っての作品でしょうか。
私自身も大好きで文句なく楽しみました。
いろいろと思い浮かべる作品はあるでしょうが私がすぐに浮かんだのはデュ・モーリアの『レベッカ』です。
今はもういない美しいレベッカを慕い続けていた家政婦という小説ですがヒッチコックの初期作品となっています。横山氏はヒッチ映画というのもあって観ておられるのでは。(私自身が映画は観てないのでそっちの内容はわかりかねますが)
男性向け作品ではほとんど女性が出てこないのに女性向けマンガで女性を描かせるとこんなに唸ってしまう作品を描いてしまう横山先生。やはりふたりいて欲しかったなああ。
とはいえそれは無理で仕方ない。
この路線は山岸凉子先生がしっかり受け継いでくださっています。
様々な後継者がいる横山光輝先生です。